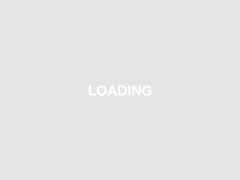イベント
ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/001.jpg) |
本セッションは,様々なゲーム開発会社が独自に進めている開発資料を保存する取り組みと,それを活用する形で実施される展覧会などのイベント開催において,どのようなプロセス上の課題と著作権などの法的問題が発生するのか。そしてそれに対して,どのような解決方法があるのかについての知見を,専門家を交えて共有するものだ。
登壇者は,スクウェア・エニックス イノベーション技術開発ディビジョン リードAIリサーチャーの三宅陽一郎氏,一般社団法人ゲーム展示協会 理事の尾鼻 崇氏,そして松田特許事務所 代表弁理士の松田 真氏の3名だ。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/002.jpg) |
スクウェア・エニックスではどのようにゲーム資料を保存し,活用につなげているのか
まずマイクを握ったのは,スクウェア・エニックスの三宅氏。現在社内で進めている資料保存のプロジェクトと,近年の活用方法について語った。
スクウェア・エニックスでは,「SAVE Project」と呼ばれる,開発資料を保存し,資産にする作業を進めているという。目的はスクウェア・エニックスの文化や歴史を明文化(文章化)することで,整理・アーカイブ化をしたうえで,社内で誰でも活用できるデータベースに保存する。
それを使えば,新たなアイデアの創出だったり,リマスター版を作る際の重要な資料になることも見込める。また,企業の歴史を整理してパブリック化を目指し,社内外で活用することは,結果的に企業価値の向上にもつながっていくという。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/003.jpg) |
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/004.jpg) |
氏によると,社内には現在,段ボール1万箱ぐらいの開発資料が存在するが,プロジェクトのサンプルとして旧エニックスにあった倉庫の段ボールから着手したとのこと。これはもっとも規模が小さいのと,管理単位が分かりやすかったからだが,それでも約50箱強ほどあったそうだ。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/005.jpg) |
このプロジェクトの成果は徐々に現れつつあり,2021年には初めてCEDECの講演に利用できたほか,そのあとの複数の講演や展示にも活用できている。
[CEDEC 2021]スクウェア・エニックスの過去資産サルベージプロジェクトや,「ワンダープロジェクトJ」開発当時の資料が紹介された講演をレポート
![[CEDEC 2021]スクウェア・エニックスの過去資産サルベージプロジェクトや,「ワンダープロジェクトJ」開発当時の資料が紹介された講演をレポート](/games/999/G999905/20210825027/TN/001.jpg)
CEDEC 2021の初日となる2021年8月24日,スクウェア・エニックスは「資料を資産へ、スクウェア・エニックスにおけるゲーム開発資料発掘プロジェクト [Wonder Project J編]」と題したセッションを行った。過去資産のサルベージプロジェクトや,スーファミソフト「ワンダープロジェクトJ」の開発資料が紹介された。
なお,ゲーム開発資料の展示に関しては,近年,国内外で活発な動向が続いている。例えば,海外ならGDC 2025の「Game History Gallery」,国内では後ほど詳しく話題が出てくる文化庁の「のこす!いかす!!マンガ・アニメ・ゲーム展」などだ。イベントで目に見える形で広まった結果,社内でも資料保存プロジェクトの理解が進んでありがたかったと,三宅氏は語る。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/006.jpg) |
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/007.jpg) |
またこういった活動は,最新のゲームタイトルを発売することによるビジネス的な価値創造とは異なり,文化や学術的な世界への影響が大きく,より広く社会一般に貢献できることを実感したそうだ。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/008.jpg) |
ただし,同時に課題も見えてきている。具体的には展示会で公開しようと思うと,「どうすれば展示会を開けるのか」「ゲーム開発資料を公的に展示するメリットは何なのか」「文化財としてゲーム資料を保存する意義」といったものが持ち上がってくるほか,その際に「展示や複製などにおける著作権」「展示などに関して問題が発生するケース」「権利者が不明の著作物」などの,法的問題が出てくることがあるそうだ。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/009.jpg) |
ここからはそれぞれ,展示会などのイベントについて,専門家である尾鼻氏と,法的問題についての専門家である松田氏にマイクが渡り,より具体的な事例について話が進んでいった。
実際に展示会を開催する際は,物理的な問題がのし掛かる
尾鼻氏は,自身もいちゲーマーとして,かつてはMMORPGを一週間で100時間プレイしていたこともあると語る。それもあって,ゲーム文化を少しでも後世に残すために活動しているという。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/010.jpg) |
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/011.jpg) |
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/012.jpg) |
イベントに関しては,すでにいくつもの開催に関わってるが,本講演ではとくに,2025年6月14日から22日にかけて国立新美術館で行われた,前出の「のこす!いかす!!マンガ・アニメ・ゲーム展」(以下,いかす!展)の事例について語った。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/013.jpg) |
いかす!展の出発点は,ゲームを「のこし」そして「いかす」ために,現状そのものや,その課題について考える展示を行いたかったからだという。持続的な保存には利活用が必要で,そのためには「動態保存」の手段を模索しなければ,次世代に残すことができない。
このような取り組みをしている方々を知ってもらい,みんなで考えていくための場所を作りたい,という思いがあったそうだ。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/014.jpg) |
イベントのキービジュアルは,マンガ・アニメ・ゲームとテーマが横並びだったので,「ゲームセンターあらし」を採用。それなら「スペースインベーダー」を展示したい,という流れになった。
その後,ゲームを公共施設に収蔵や展示するなら,どのような課題があるかを考えた。まずは,スペースインベーダーの資料を展示するために,タイトーに許諾を得ることから始める。さらに展示物に関して,すべての企業に許諾を得ることに挑戦した結果,無事に快諾をもらえたという。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/015.jpg) |
なお,原則として,展示の際はすべての資料の許諾を得るようにしているが,これは法律面の問題もさることながら,企業側に(「迷惑だろう」としつつも)展示申請の稟議を通す経験を積んでもらいたい,という側面もある。というのも,次に似たような事例があった場合,経験があれば,よりスムーズに許諾が通る可能性が高まると考えているためだ。
実際に5〜10年と続けてきて,徐々に円滑に進むようになったと感じているとのこと。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/016.jpg) |
実際のイベントにおける搬入,設置,保守にも話が続く。いかす!展で利用した国立新美術館は,もともとメディアアートなどが展示されており,スペースに関しては大きな問題はなかったという。エレベーターも大型のものが用意されており,その点でもトラブルはなかったそうだ。
これが会場によってはエレベーターのサイズなどがネックになり,とくにアーケード筐体は大きくて重い(ピンボール筐体で重さ100kg以上,大型筐体だと300kgを超えるものもある)関係上,場合によっては何人もの大人が,階段で運ぶ事態に陥る。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/017.jpg) |
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/018.jpg) |
展示には「見える収納庫」という,収蔵/保守/展示を兼ね備えるテストケースが使用され,さらに隣には「見える作業部屋」という,日本ゲーム博物館の作業部屋をそのまま移設し,メンテナンスについても見られるように工夫した。
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/019.jpg) |
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/020.jpg) |
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/021.jpg) |
これは部品がなくなったり,技術者が減ったりして,修理すること自体が困難になっていくという課題を認識してもらうための展示だったが,想像以上に筐体の故障が相次いだため,実際に活用することになってしまったとのこと。
しかし,ただでは転ばず,リアルタイムで修理すること自体も展示にしてしまったわけだ。これを見ることができた人は,逆にラッキーだったかもしれない。
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/022.jpg) |
![画像ギャラリー No.023のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/023.jpg) |
それ以外にも,ゲームは大きな音を発生させるので,ある程度の防音対策が必要だし,さらにブラウン管が失われていくなかで,どうやって稼働時と同じ体験を再現するかも悩んだという。
![画像ギャラリー No.024のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/024.jpg) |
本講演のテーマであるゲーム開発資料に関しては,NINTENDO64で発売された「ワンダープロジェクトJ2」の資料を“段ボールごと”展示するという,インパクトのある手法が採られた。
これは,尾鼻氏が現代美術的な見せ方をしたかった……というのもあるそうだが,開発に携わった人以外に,資料にはどのような種類があって,どれほどの量があるのかを知ってもらいたかったからと振り返る。
![画像ギャラリー No.025のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/025.jpg) |
さらに,展示に関連した企画で,実際の資料を使ってトークセッションを行えたと尾鼻氏は述べる。こういった開発資料は,ぜひセットで後世に残していきたいと,意気込みを語っていた。
![画像ギャラリー No.026のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/026.jpg) |
最後に尾鼻氏は,文化財の変化スピードを少しでも遅らせて破損を防ぐ,保存方法の「予防的保存」には,(ほかの要素も当然あるが)湿度の管理が非常に重要だと強調した。
![画像ギャラリー No.027のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/027.jpg) |
また,ゲームはプレイするものであるから,動作する状態での保存が重要で,とくにアーケード筐体は巨大で保管コストがかかってしまう。産学官の連携の実現はまだ道半ばで,とくに開発関連資料に関しては遅れている事実があり,ゲーム関連の展示は,まだ収益性が低いという課題(今回の展示でも,8日間で来場者は約8000人だったそうだ)などがあるとして,マイクを置いた。
![画像ギャラリー No.028のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/028.jpg) |
ゲーム関係資料の展示には,どのような法律が関わってくるのか?
3人目のスピーカーは松田氏だ。ここからは,主に法律面の問題について,展示に関わるものが話題に上がった。
![画像ギャラリー No.029のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/029.jpg) |
まず,資料の展示に関係する知的財産権だが,特許権,意匠権,肖像権など様々な権利が関わってくる。そのなかで,とくに重要なのが著作権とのことだ。これだけ権利があるので,基本中の基本として許諾は受けてほしいと松田氏は述べた。
![画像ギャラリー No.030のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/030.jpg) |
さらに,一言で著作権といっても,主立ったものだけで,スキャンやコピーに関する複製権,そうしたデータをネット上で公開するときに関係する公衆送信権,映像を上映するときに関連する上映権,博物館に並べるときに重要な展示権など,非常にたくさんの権利があると付け加えた。
![画像ギャラリー No.031のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/031.jpg) |
ここで一番関連がありそうな展示権だが,これは「原作品」に効果が発揮される権利で,例えばコピー(複製)したものを展示するときは,複製権が関係する話になってしまうそうだ。
裏を返せば,展示権が引っかかって展示できない場合,コピーしたものを展示すればいいように思える。しかし,そもそも観覧者は「オリジナルを見たい」と思う可能性が高いので,そのあたりがネックになるかもしれないと語っていた。
![画像ギャラリー No.032のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/032.jpg) |
ただ,いずれにしても「展示するから,関係する権利は展示権だ」ではなく,場合によっては複製権が働く点には留意してほしいとのこと。また条文には「美術」と書かれているが,いわゆる美術品を単に指しているのではなく,資料でもイラスト(絵)が入っていると,こちらに分類される可能性があり得るそうだ。
また上述のとおり,映像を流すときには上映権が関係してくるが,一定の条件を満たすと(権利者の)権利制限が発生し,許諾なしで上映可能な場合もあるとのこと。
具体的には「非営利目的かつ無料の場合」なのだが,これならすべてが許諾不要というわけでもなく,例えば展示会で入場料を徴収したり,あるいは実演家に報酬を支払ったりすると,この条件を満たせなくなってしまう。
繰り返しになるが,やはり取れる許諾は取っておく,というのが基本なのだろう。
![画像ギャラリー No.033のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/033.jpg) |
![画像ギャラリー No.034のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/034.jpg) |
ただ,その一方で,許諾を取りたくても取れない場合がある。それは権利者が不明になっている場合で,権利者自体が誰か分からなかったり,あるいは亡くなった権利者の相続人が不明だったりする状況だ。
![画像ギャラリー No.035のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/035.jpg) |
こういった場合は,文化庁長官が権利者の代わりに利用を認めてくれる,「裁定制度」という仕組みがあるため,こちらの利用を目指すことになる。しかし,手順はなかなかに複雑かつ手間がかかるようで,スライドにある権利者を探すための「相当の努力」を果たすという部分は,一文字違いの「相当な努力」が必要だと振り返っていた。
![画像ギャラリー No.036のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/036.jpg) |
なお,この裁定の利用には,ライセンス料と同等の供託金(補償金)を支払う必要があるのだが,これが不要な主体があるという。それは,国や地方公共団体といった,公共性のある組織や団体だが,これには独立行政法人が入っていて,これは前出の,いかす!展を開催した国立新美術館も含まれる。
つまり,企業と国立美術館の協力体制は,供託金不要で進められる可能性があり,非常に合理的なのではないか……とのことだ。
![画像ギャラリー No.037のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/037.jpg) |
ちなみに,この裁定制度を使い,あとから権利者が出てくるパターンだが,実際はかなり少ないとのこと。松田氏によると10%にも満たない(数%程度)と語っていたので,(供託金が不要な組織と)組んでやってみる価値はあるとのことだった。
この裁定制度の利用は,ゲームビジネスでも利用が着実に増えており,2021年には1件しかなかった利用例が,2025年はすでに7件も確認できているという。
これはまさに「道ができた」といえる状態であり,さらに復刻以外にも2023年にはゲーム実況に使われるなどの例もあるので,ゲーム開発資料の展示のために複製を行うような場合でも,利用できる可能性はあるだろうと,氏は語る。
![画像ギャラリー No.038のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/038.jpg) |
![画像ギャラリー No.039のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/039.jpg) |
ただし,注意点として,この制度は裁定が降りるまでに時間がかかり,実例として着手から半年かかったので,早めに動くのが重要だとした。
また,あくまで裁定は「利用者」という立場になるだけで,別に著作権を取得できる(著作者になる)わけではないことも,留意したいそうだ。
![画像ギャラリー No.040のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/040.jpg) |
![画像ギャラリー No.041のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/041.jpg) |
最後に,具体的に展示などで問題が起きやすいケースとして,上映権を例に挙げた。それは,ゲーム筐体をただ展示するだけなら問題は起きづらいが,電源を入れる(動態展示する)と「上映」扱いになり,許諾なしで入場料を徴収していた場合,上映権侵害になってしまうというものだ。
![画像ギャラリー No.042のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/042.jpg) |
また,著作権法や特許法などは条文があり,それに従えば利用に問題はないが,肖像権やパブリシティは条文がないので,何がOKで,何がNGなのか判定しにくいとのこと。
例えば,開発者の顔を展示に含めたい場合,これは肖像権になるので,許諾をきちんともらうか,ダメなら展示を控えるほうがよい,として松田氏はマイクを置いた。
![画像ギャラリー No.043のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/043.jpg) |
![画像ギャラリー No.044のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/044.jpg) |
マイクは再び三宅氏に戻り,ゲーム開発資料を扱う上での企業の問題として,資料の規模が大きいので管理体制の整備が必要だが,ただでさえ量が膨大なのに現在進行形で増え続けていると述べた。
そして,所有者や権利者が分かりにくいので,公開可能かどうかも判断しにくく,さらに資料は,社内的な価値と社外的な価値が異なることも課題になっているという。
![画像ギャラリー No.045のサムネイル画像 / ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/045.jpg) |
これらは企業内だけで解決するのは難しく,やはり法律の専門家と学術関係の連携が必要だとして,講演を締めくくった。
なお,講演のラストに行われた登壇者3名のディスカッションで,三宅氏の「(イベントなどを行いたいときに)どのタイミングで相談したらいいのか」という質問に,尾鼻氏と松田氏の両者が「思い立ったらなるべく早く」と語っていたのが印象的だった。実務的な面でも法律的な面でも,なるべく早く準備を始めたほうがいい,ということのようだ。
「CEDEC 2025」公式サイト
4Gamer「CEDEC 2025」関連記事一覧
- 関連タイトル:
 講演/シンポジウム
講演/シンポジウム - この記事のURL:


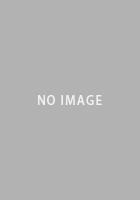
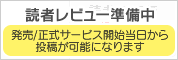
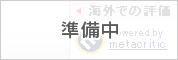






![ゲーム開発資料を保存し,展示などへの活用を目指す際には何が問題になるのか? 押さえておきたいイベントと法律の両面での壁[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250731073/TN/046.jpg)