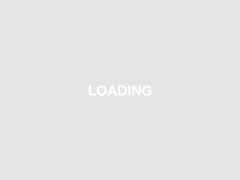イベント
生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/001.jpg) |
本講演は,近年急激な進化が進むAI(人工知能)について,現行の生成AIやAIエージェントに代わる次世代の方式を考えるもので,慶應義塾大学 理工学部 教授の栗原 聡氏が登壇した。
AIの専門家である栗原氏は,ゲームについてそこまで明るくはないとしつつも,ゲーム開発を含め,AIの利用の有無が社会において,未来に大きな影響を与えるだろうと語った。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/002.jpg) |
AIの本来の用途は“効率化ではない”
まず栗原氏は,AIの歴史についてざっと振り返った。
「人工知能」という言葉が使われ初めて現在では70年ほど経つが,それまで何度もブームと冬の時代を繰り返してきたのだという。1960年代前後の第1次ブームは「探索」,1980年代前後の第2次ブームは「知識処理」が話題になったが,社会インフラやコンピュータの性能が不十分であり,その後は冬の時代に突入していった。
だが第3次といえる現在の「機械学習」のブームは,コンピュータの性能向上によりディープラーニングを中心とする技術が社会実現可能なレベルに達し,2022年にChatGPTが登場して以降,さらにブームが加速する状態になっているという。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/003.jpg) |
また物理学賞や化学賞など,人間がAIを使用しノーベル賞を受賞するような現象が起こっている以上,AIを活用しないとパフォーマンスに影響が出て,イノベーションで勝てなくなる事態も起こりうる。
現状のAIはまだ人間のサポートという立ち位置だが,2050年頃に自律型AIが自ら仮説を立て,実験をおこない,AI自体がノーベル賞を取ることを目指すプロジェクト「ノーベル・チューリング・チャレンジ」も進んでいるのだという。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/004.jpg) |
その一方で大規模なAI構築には膨大なリソースが必要であり,ビッグテックと呼ばれる世界的な巨大IT企業と同じ規模のものが,日本国内の個々の企業でできるかといえば,現実的には難しい。
またAIの導入やDX(デジタルトランスフォーメーション)化は,ビジネスの最終的な価値に結びつけることこそが重要であり,トップがブームに慌てて導入し,実際の業務では単に情報が動くだけで終わって,結果(ものつくり)が取り残されてしまう,なんてことでは意味がない。
つまり,単にAIなどの導入よるデジタル化することだけが目的化してしまっては,まさに本末転倒である,というわけだ。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/005.jpg) |
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/006.jpg) |
また,現状のAIは投資に見合った利益が出ていないとされるが,それはビッグテックの収益源が主な広告であり,さらに巨大企業同士が開発のチキンレースを行っているからだという。そのためAIバブルが弾ける可能性自体は否定しないが,それはAIが使えないからではなく,“まだ本来の使い方ができていない”だけと考えているそうだ。
さらにAIというと,まずデータに効果が表れやすい「効率化」という面で評価されたり,語られたりしがちだが,真に重要なのはイノベーションを起こすことであり,逆に効率化だけ目指してもイノベーションは生まれないと,栗原氏は語る。
イノベーションとはなにか,AI活用でどのようにイノベーションを起こすか
次に栗原氏は例を出しながら,実際のイノベーションについて語った。
「イノベーション」という言葉自体は抽象的だが,栗原氏は解釈のひとつとして「因果を結びつける」ものと,考えているそうだ。
具体的には,通常人間は「○○が起こると,××が発生する」という認識をするが,両者が遠い存在であると,それを結びつけるのが非常に難しい。イノベーターと呼ばれるような特殊な人であれば,それも可能であろうが,そうでない一般人でもAIがヒントや仮説を出すことによって,より簡単にその因果を結びつけることができるのではないか……というのが,栗原氏の意見だ。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/007.jpg) |
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/008.jpg) |
実際に2023年から2025年にかけて,NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)によって,AIを活用して新作マンガの「ブラック・ジャック」を生み出すという,「TEZUKA2023」というプロジェクトが行われた。
ここではプロのクリエイターではあるが,AIの専門家ではない脚本家でも納得できるプロット(物語と登場人物)がGPT-4で生成できるように,インタラクティブなプロンプト生成AI(御用聞きAI)が作られた。そして使用者のスキルに依存しない形でプロンプトを成形したり,生成するコンテンツの特徴を自由に入れ込んだりすることに成功している。
これは今でいう,AIエージェント(多少の判断力を持ち,簡単なタスクの一部を自律的に実行するAI)のはしりではないか……としていた。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/009.jpg) |
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/010.jpg) |
また,このときに共同でプロジェクトを行ったクリエイターに「(AIのサポートが入ると)思考の仕方が根本的に変わる」と言われて,ハッとしたそうだ。というのも創造的な作業の場合,人間同士で共同作業を行うとスケジュールなどの関係から,やり取りするのに数日から一週間程度掛かることも珍しくない。だが相手がAIならば,ほとんど間を置かずレスポンスが返ってくるので,短時間で集中したまま作業ができるからだ。
その一方で使い方そのものは,あくまで本人の能力(イノベーション力)に左右されるし,特に日本の場合はイノベーション云々より,単純な効率化のほうが評価される場面が多いのではないか……とも語っていた。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/011.jpg) |
道具型のAIから,自律型のAI「BuddyAI」へ
続いて栗原氏は,現在のAIはあくまで道具に過ぎないが,将来的には自律型AIの時代がくるだろうとした。だがまず目指すべきはAIエージェントの開発で,これは日本が得意とするジャンルであろうし,さまざまなものが登場することに期待しているそうだ。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/012.jpg) |
しかし,同時に現在の社会は国際的にも分断が進み,寛容さも失われつつあることが懸念材料になっていると栗原氏。道具型のAIは人間の利得最大化が目指されるので,その方向性でAIが自立性を獲得してしまうとより一層,他者からの搾取を促進し,利他的な行動の抑制につながる可能性が否定できないからだ。現状では自律型AIのガイドラインも,国内では存在しないとのこと。
そういった観点で栗原氏は少し前まで,「おもてなし」が良いのではないかと考えていたそうだ。このおもてなしとは,客観的や内面的な相手の状況を理解したうえで,適切な行動を望ましいタイミングで(相手が求める前に)能動的に行うこと。「気配り」という言いかたもできる。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/013.jpg) |
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/014.jpg) |
だが現在は,おもてなしは道具の延長線上に過ぎないのではないか……と考えるようになったそうだ。なので理想は「おもてなし」より「思いやり」で,相手の要求を先回りしてかなえるのではなく,状況によってはあえて苦言を呈したり,何かを拒否したりといった行動が必要で,将来的には十分ここまで可能になるのではないかと語っていた。
そのような考えに至った原因は,インターネットやSNS,そして場合によってはAIがデマやフェイク情報の拡散に利用されたり,フィルターバブルによって特定の情報に晒され続けたり,陰謀論が一気に広まったりと,テクノロジーがサイバー空間のみならず日常生活自体も巻き込んだ影響を与えるようになったためだという。
技術の発展はさまざまな恩恵をもたらした一方,物事に対する脊髄反射的な行動が増えたり,不寛容さが広まったりと,同質化・均質化的な異なるものの排除に向かうようになってしまった。
つまりテクノロジーの加速的な発展は,逆に人類の限界点をもたらしてしまったのではないか……という話だ。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/015.jpg) |
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/016.jpg) |
こういった観点から,栗原氏は望ましくないテクノロジーによる変容を元に戻す手段として「BuddyAI」というものを考えたそうだ。これは個人がそれぞれ専用に持つ高度自律汎用AIのことで,BuddyAIは自分のバディ(利用者)に適応していき,逆に利用者はBuddyAIを信頼していく。日本語としては,相棒に近い存在だ。
自助や強制的な外部からの介入では変えることができない行動の変容も,自らが信頼したモノなら納得して変えられるかもしれない。これがBuddyAIのコンセプトであり,いってみればドラえもんの作中における(ドラえもんと)のび太との関係と同じようなものだ。
そしてAIなら,さまざまな物体やシステムに“憑依”して活用ことができるので,例えばPCで何かを閲覧する時に補助したり,自動運転で利用したり……といった形での活用も期待できる。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/017.jpg) |
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/018.jpg) |
ただし現在のAIをBuudyAIに進化させるには,「状況の理解や空気を読む力」「他者の意図を理解する能力」「反実仮想な思考」「臨機応変にするべきことを決定する能力」「臨機応変な振る舞いの変更」の5種類が必要だとした。現状,最後の2つはまだ難しい状態だが,最初の3つは巨大LLMによって壁が破壊されつつあり,5年から10年ほどの未来に登場する次世代のAIなら,完全に壁が壊せる時代がきそうである,とのことだ。
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/019.jpg) |
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/020.jpg) |
また実際にどうやって壁を突破するかだが,海外のビッグテックが開発しているような大規模な基盤モデルを日本が後追いするのは(予算的に)無理であるし,ここまで来るとビッグテックですら可能かわからないので,別のアプローチが必要という見立てだそうだ。技術としては古典的なシンボル型のAI,それも別に昔に戻るのではなく,現代の技術を加味しての「新生シンボル型AI」が脚光を浴びるのではないか……と,予感している。
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/021.jpg) |
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/022.jpg) |
最後に栗原氏は,これはビッグテックではない日本勢が,実用性のあるスケールしたAIを構築するチャンスであり,ぜひ次世代AIの実現に向けたチャレンジをおこなってもらいたいとして,講演を締めくくった。
![画像ギャラリー No.023のサムネイル画像 / 生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/023.jpg) |
なお講演終了後の質疑応答で栗原氏は,「あえて苦言を述べて気分を害するかもしれないAIを(心地よい他のAIより優先して)利用者が使ってくれるのか?」という問いに,バディがいうならしょうがないと感じられる信頼感を得られるアプローチが必要だという。
それこそ初等教育からでも「こういうものが必要だ」と感じられるような地道な教育と,空気感の形成が重要なのではないかと述べていた。つまりAIが人間に合わせるだけでなく,人間側もAIの時代に合わせて変わっていく必要がある……そういった知見が得られた講演であったと,著者は感じた。
「CEDEC 2025」公式サイト
4Gamer「CEDEC 2025」関連記事一覧
- 関連タイトル:
 講演/シンポジウム
講演/シンポジウム - この記事のURL:


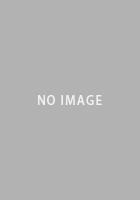
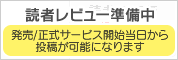
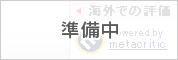






![生成AIやAIエージェントの次に来るネクストAIとは何か? “おもてなし”にとどまらない次世代“BuddyAI”の形とは[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250724053/TN/024.jpg)