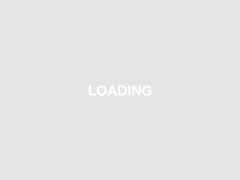イベント
「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]
このセッションでは,両氏が手がけてきた作品や,名作アドベンチャータイトルの構造が解説されたほか,現在両氏が関わっている新作「シブヤスクランブルストーリーズ」についても語られた。
アドベンチャーゲームの構造解説については,先に掲載したダイジェスト版でレポートしたが,本稿はそのほかの部分まで含めた詳細版として掲載する。
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/001.jpg) |
講演の冒頭では,両氏がこれまで手がけてきた作品が紹介された。4Gamer読者には説明するまでもないタイトルが並んだのだが,イシイ氏がチュンソフト入社前に手がけたタイトルは,知らない人が多いかもしれない。氏は19歳の頃からゲーム開発に参加し,テキストやイラストを手がけていたそうで,「最近隠さずに言うようになった」とのこと。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/002.jpg) |
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/003.jpg) |
北島氏はもともと新聞記者で,そこからノンフィクションライターに転身した。ゲームのシナリオを書くようになったのは,「3年B組金八先生 伝説の教壇に立て!」で,「ノンフィクションのリアリティが欲しい」と考えていたイシイ氏から声をかけられたことがきっかけだったそうだ。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/004.jpg) |
続いて本題となるアドベンチャーゲームの構造解説へ。イシイ氏は,「弟切草」や「かまいたちの夜」という2つのノベルゲームの登場によって,ゲームとシナリオの関係が大きく変化したと考えている。
それ以前は,シナリオが終わったらゲームが始まり,ゲームが終わったらシナリオが始まる……という“サンドイッチ”構造のものが多かったという。イシイ氏は「シナリオかゲームのどちらかが面白ければプレイできる」と,この構造のメリットを挙げつつも「システムに広がりがない」とした。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/005.jpg) |
「弟切草」と「かまいたちの夜」によって,シナリオ自体をゲームにするような構造が登場したのだが,両作の構造は大きく異なる。
選択肢によって分岐するのは同じだが,「弟切草」はあみだくじ状の構造になっているのが特徴。あちらこちらの展開に飛べるため,“さっきまで恋人だと思っていた人がいきなり怪物になり,また恋人に戻る”といった突飛な話もあれば,とてもいい話としてまとまることもある。それが「弟切草」の面白さにもなっているのだが,イシイ氏はこの構造について「体験の均質化ができない」と表現した。
「かまいたちの夜」はピラミッド状の構造を採用し,分岐の後に別の展開へ戻ることはできなくなった。これによって因果律が正しくつながるようになったのだが,イシイ氏は「それだけならゲームブックでもできる」と語り,本作の凄さは「入口にグッドエンドを作ったこと」だとした。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/006.jpg) |
「かまいたちの夜」は,雪に閉ざされたペンションで起こる殺人事件を題材にしたミステリー作品で,ゲームの序盤にある選択肢を正しく選んでいくことで,事件解決(グッドエンド)へとたどり着ける。
かなり難度が高いため,多くの場合は正しいルートから分岐したバッドエンドを見ることになるが,そこに至る途中でさまざまなヒントが得られるため,プレイヤーはそれを踏まえてまた最初からチャレンジする。
イシイ氏は,一度死んでからグッドエンドが開くのではなく,最初から開いているところがとても美しく,衝撃的だったと語った。
そして,プレイヤーがバッドエンドを何度も見ながらチャレンジを繰り返す「ループ構造」も“発明”だった。これはゲームのみならず,映像作品にも広がって,今や「ループもの」という1つのジャンルになっている。イシイ氏は「SF小説などにもループものはあったので,ゲームがすべてではないが,ゲームによってループ構造への理解は深まったのではないか」と話した。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/007.jpg) |
続いて紹介されたのは,複数キャラクターの視点で展開される群像劇アドベンチャーの構造だ。イシイ氏は「マルチサイト」と呼んでいるという。
マルチサイトの特徴は,ある登場人物の選択が,本人ではなくほかの人物に影響を与える「他人分岐」にあるのだが,これによって「提灯分岐」が持つ意味合いも大きく変わったという。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/008.jpg) |
提灯分岐は,上の画像の右上に描かれているもので,「どちらを選んでも(本人には)影響がない」分岐。「右の道を行くか? 左の道を行くか?」という選択肢のどちらを選んでもその後の展開は同じといった感じのもので,1人の主人公で展開されるアドベンチャーゲームでは,あまり意味を持たない。
だが,この提灯分岐を他人分岐として使うと,「何気ない選択が他人の運命を変える」という構図を作れるわけだ。
上の画像は2人で展開されるマルチサイトだが,3人以上になると,その構造はさらに複雑になる。下の画像にその構造が描かれているが,ある選択が誰に影響するのかを示すには,本来三次元で表現されるべきもので,イシイ氏はA4の紙を円筒状に丸めてそれを説明した。
「428 〜封鎖された渋谷で〜」のキャラクター選択画面が円筒状になっているのは,あるべき姿に倣ったというわけだ。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/009.jpg) |
こうなってくると,シナリオを書くのが大変になるのは想像がつく。北島氏はマルチサイトの制作に当たって,時間を強く意識しているとのこと。そのために,マップを用意して各キャラクターの行動範囲やルートを作り,“横時間”を整理して各キャラクターのストーリーが矛盾を生まないようにしているという。
さらに,キャラクター同士が遭遇したときのリアクションをよりリアルにするため,キャラクター設定の密度は普段以上に上げているそうだ。
北島氏は,マルチサイトのシナリオ制作は,ゲームシステムを意識するディレクターとの二人三脚であるとも語った。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/010.jpg) |
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/011.jpg) |
イシイ氏はマルチサイトアドベンチャーゲームに欠かせないものとして「未来をセーブする」機能を挙げた。
これは一度ルートを開放した後,序盤の選択肢を変えてその影響を確かめたり,元に戻したりができる機能のこと。人によっては「できて当たり前」と感じるかもしれないが,アドベンチャーゲームには古いシステムを採用しているものも多く,序盤の選択肢を変えると以降は初回と同様のプレイが必要になるものもあるそうだ。この機能がしっかり整備されていると,プレイヤーだけでなく,開発のしやすさにもつながるという。
続いては,新たな可能性がありそうなアドベンチャーゲームのシステムが紹介された。
その1つは「オープンワールドアドベンチャー」。これは「複数あるシナリオをバラバラの順番で体験し,その時系列を想像しながら物語を理解する」というもので,「Her Story」「十三機兵防衛圏」「ZERO ESCAPE 刻のジレンマ」などが該当するという。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/012.jpg) |
もう1つは「ローグライクアドベンチャー」。これはシナリオがランダムに発生するもので,「グノーシア」や,イシイ氏が開発に参加している「Depth Loop(仮題)」などがある。氏は「小説の神は作家で,ゲームになると開発者とプレイヤーだが,ローグライクアドベンチャーはそこにゲームシステムが割り込んでくる」と表現。そういった神々による思いもよらぬ展開に,主人公たちがどう対峙するかを見てほしいとした。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/013.jpg) |
そんなイシイ氏と北島氏が中心となって進めているプロジェクトが「シブヤスクランブルストーリーズ」だ。7月25日に終了したクラウドファンディングは,目標額の10倍以上となる5400万円超を集めるなど,話題となっている。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/014.jpg) |
イシイ氏は,2008年にリリースした「428 〜封鎖された渋谷で〜」がヒットしてから,その後を継ぐような実写アドベンチャーゲームを誰かが作ることを期待していたそうだが,15年が過ぎてもその動きがなく,その一方で「ああいうゲームを作らないのか」と聞かれることが多かったため,自分たちで作ろうと決意したという。
そこまで待った理由としては,実写アドベンチャーの制作が非常に大変で,開発費もかなりのものになったことが挙げられた。だがイシイ氏は,それからさまざまな経験を積んだ今なら,そういった問題を乗り越えられると感じているようで,「クラシックなノベル形式で,みなさんが期待するマルチサイトなどの仕組みも取り入れながら,見たことがない世界へみなさんを連れて行くようなものにしたい」と意気込みを語った。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/015.jpg) |
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/016.jpg) |
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/017.jpg) |
ここでセッションは終了となり,質疑応答に移った。ほかのセッションよりも長めの時間が設けられ,興味深い質問もいくつかあったので,紹介しよう。
最初は,「『Detroit: Become Human』など,海外のアドベンチャーゲームと日本のアドベンチャーチームとの違い」について。
イシイ氏は,「『Detroit: Become Human』や『Heavy Rain』などは,ループ構造にあまり興味がなく,逆に日本のアドベンチャーゲームが気にしていないところにこだわりがある」と回答。具体的には,「悲劇の体験性」だという。
日本の場合,悲劇はバッドエンドであり,それはループへとつながっていくことが多い。つまりは途中経過だ。
イシイ氏も,あるすれ違いによる悲劇で物語が終わる「ロミオとジュリエット」をゲーム化できるだろうか,と考えたことがあるという。何らかの問題を解決するという性質を持ったゲームが,悲劇を真のエンディングとできるだろうか,というわけだ。
だが海外のアドベンチャーゲームは,「自分の指を切り落とす」「誤って人を撃ってしまう」といった悲劇そのものをインタラクティブ性によってしっかり体験させようとする意図があるという。それはフローチャートからも感じられるそうで,イシイは日本と海外のアドベンチャーゲームでは発想が大きく異なることを説明した。
続いては,「ローグライクアドベンチャーのサイコロを,生成AIに置き換えて,シナリオをつむいでいくことはできるでしょうか?」という質問。
イシイ氏は,「生成AIではないが」と断りを入れつつ,ストーリー性を語れるだけの思考AIが,人を楽しませることができれば,ローグライクアドベンチャーは進化していくだろうとした。
生成AIについてはそれらとまったく別物であると考えているそうで,「ローグライク以上にとんでもないものが生まれる可能性がある」と期待を語った。
次の質問は「イマーシブ・フォート東京」などで楽しめる体験型演劇をどう分析するか,というもの。イシイ氏は,上海で上演されている「UME PLAY」などにも触れながら,このジャンルをデジタルゲームに落とし込むことを考えていると明かした。ただ,人によってフォローされている部分も多いため,そのあたりをどうするか,勉強中だそうだ。
続いては,「ローグライクアドベンチャーは,シナリオの体験とシステムの体験がバッティングしないか」という質問。
北島氏はこの質問に「先に書いたシナリオをゲームに載せる場合もあれば,ゲームシステムに合わせてシナリオを書くこともある」と切り出し,それによって物語性は変わってくるかもしれないとした。だが,北島氏が主に手がけているのは後者の方ということもあり,「そこでシナリオやキャラクターの面白さがスポイルされることはない」と説明した。
最後は「複雑で重層的なシナリオを作れるライターの育成は可能か」というもので,これを聞いた両氏はまず苦笑いでその難しさを表現。イシイ氏は「小説も漫画も,1人の勝者に1万人の敗者がいるような世界」であり,作家を育てるのは「オーディション的な構造しかない」と話した。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / 「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/018.jpg) |
「CEDEC 2025」公式サイト
4Gamer「CEDEC 2025」関連記事一覧
- 関連タイトル:
 シブヤスクランブルストーリーズ
シブヤスクランブルストーリーズ
- この記事のURL:


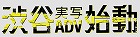
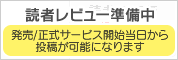
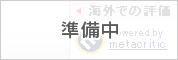






![「シブヤスクランブルストーリーズ」が目指す,ADVゲームの先。イシイジロウ氏と北島行徳氏によるセッションの詳報[CEDEC 2025]](/games/905/G090534/20250728044/TN/019.jpg)