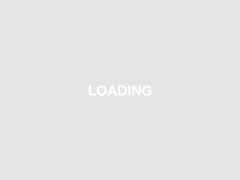イベント
フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/001.webp) |
本セッションは,フロム・ソフトウェア 3Dグラフィックセクション 3Dグラフィックアーティストの佐藤秀憲氏と片平怜士氏が,「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE」と「ELDEN RING NIGHTREIGN」の背景グラフィックス制作において活用した背景レイアウトの手法と,その活用事例を紹介したものだ。
うちセッション前半部分は,先に掲載した記事でお伝えしているので,今回はその後半部分――背景レイアウトの活用事例を見ていこう。
「ELDEN RING」の世界はいかに構築されたか。フロム・ソフトウェアが明かす,背景レイアウトの品質と印象を強化する手法[CEDEC 2025]
![「ELDEN RING」の世界はいかに構築されたか。フロム・ソフトウェアが明かす,背景レイアウトの品質と印象を強化する手法[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250723068/TN/033.webp)
国内最大級のゲーム開発者会議「CEDEC 2025」で2025年7月23日,「背景レイアウトから読み解く,『ELDEN RING』の世界」と題されたセッションが開催された。本稿では,セッション前半に紹介された背景レイアウト手法についてレポートする。
- キーワード:
- PC:ELDEN RING NIGHTREIGN
- PC
- RPG
- MO
- バンダイナムコエンターテインメント
- ファンタジー
- フロム・ソフトウェア
- プレイ人数:1〜3人
- プレイ人数:1人
- 協力プレイ
- PS5:ELDEN RING NIGHTREIGN
- PS5
- PS4:ELDEN RING NIGHTREIGN
- PS4
- Xbox Series X|S:ELDEN RING NIGHTREIGN
- Xbox Series X|S
- Xbox One:ELDEN RING NIGHTREIGN
- Xbox One
- イベント
- ライター:大陸新秩序
- CEDEC/コ・フェスタゲーム開発者セミナー
- CEDEC 2025
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/002.webp) |
「ELDEN RING NIGHTREIGN」公式サイト
「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE」の事例紹介
「SHADOW OF THE ERDTREE」からは,背景レイアウトの難度が低い順に「青海岸」「墓地平原」「影のアルター」の3エリアの事例が紹介された。
青海岸は本DLCの中でもとくに幻想的な雰囲気の場所だが,レイアウトするうえでの大きな制限はなかったため,アーティストはビジュアルのみに集中し,自由に作業できた。このため作業としての難度は低めだったとのこと。
このエリアの品質と印象を高めるための取り組みとしては,まず動線を単調にしないことが挙げられた。具体的には,設計段階では直線だった動線に,曲線を混ぜることで直線の印象を崩している。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/003.webp) |
また要素が左右に偏らないよう,バランスのよい配置を心掛けたという。具体的には左右非対称にする,グループ単位で交互に配置する,墓や石棺の向きや配置を不規則にするなどである。さらに画面の中央以外に視線が誘導されないよう,高さのある要素を配置したそうだ。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/004.webp) |
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/005.webp) |
青海岸における違和感を生む要素は,「光る花」だ。通常,花や草はプロシージャルで自動配置するのだが,このエリアの「ビューポイント」(集中的に品質を上げる場所)では,レイアウトにおける重要な要素である光る花を手動で配置し,品質を高めている。
これは近景の花に限らず,部分的にではあるが,遠くの花畑まで手動で配置したという。また遠くの花畑は手描きのテクスチャとなっており,ビューポイントから見たときに最適な密度や明るさになるよう調整が施されている。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/006.webp) |
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/007.webp) |
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/008.webp) |
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/009.webp) |
墓地平原は,「SHADOW OF THE ERDTREE」でプレイヤーが最初の訪れるエリアだ。そのためほかのエリアよりも強い印象にする必要があったという。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/010.webp) |
またゲームデザインの要件が「広大なフィールドを表現すること」だったため,近景に「ランドマーク」(視線を誘導したい要素)以外の大きなパーツを配置しないという制限が設けられていた。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/011.webp) |
以下のスライドに掲載された画像は開発中のもので,画面の下半分が単調な地面になっている。これは大きく変更できないため,開発初期には樹木などを配置して単調さをなくす提案をしたそうだが,ゲームデザインの要件を満たせないため却下されたとか。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/012.webp) |
そこで採用されたのが,遠景に要素を詰め込んで近景の単調さを打ち消す方針だった。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/013.webp) |
クオリティアップを行う前のレイアウトでは,要素のアウトラインが直線で構成されていたり,空や崖が似た模様の繰り返しになっていたりして単調さを感じさせる。加えてランドマークである巨大な樹木にも特徴がなく,印象が弱くなっている。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/014.webp) |
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/015.webp) |
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/016.webp) |
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/017.webp) |
それらの問題を修正したのが,以下のスライドに掲載された画像である。
具体的には崖の直線だった部分を複雑なシルエットに変更した。また崖の表面にフォグのグラデーションとライトシャフトを追加し,縦方向と奥行きで色を変化させた。さらにライトシャフトによる斜めの直線を重ねることで,見た目が複雑になっている。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/018.webp) |
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/019.webp) |
空はランドマークに向かって明るくすることで,単調さを軽減した。加えて,コンセプトアーティストがランドマークの樹木を独特なデザインに作り替えたことから,印象が大幅に強化されている。
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/020.webp) |
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/021.webp) |
このように修正を施したことから品質と印象は改善したが,しかし近景の単調さを打ち消すほどではなかったという。そこで強烈な違和感になる要素として,ランドマークの樹木に強大なベールを加えることにしたのである。
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/022.webp) |
![画像ギャラリー No.023のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/023.webp) |
影のアルターは墓地平原の隣にあるエリアで,「SHADOW OF THE ERDTREE」の中でもとくに陰鬱な場所である。このエリアのレイアウトには,「墓地平原と同じリソースを使う」「ランドマークが画面に対して大きい」という2つの要件があったという。
![画像ギャラリー No.024のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/024.webp) |
墓地平原と同じリソースを使う理由は,メモリや工数の都合でユニークなものをあまり作れなかったからだ。結果として,最初は墓地平原と変わり映えしない見た目で,同じようなビジュアルが連続する体験となっていた。これは非常に良くない状況である。
![画像ギャラリー No.025のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/025.webp) |
そうした印象を変えるために,色彩の変更が行われた。セピア調で枯れた雰囲気だったものが,黄色を主軸とした色合いとなり,さらに違和感になる要素として,黒い縦線も追加されている。この縦線はフォグで周囲に馴染んでしまうと意味が薄れるため,減算処理を施して目立つようにしているとのこと。
![画像ギャラリー No.026のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/026.webp) |
![画像ギャラリー No.027のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/027.webp) |
もう1つの要件であるランドマークが画面に対して大きいことは,より深刻な問題だった。このエリアのランドマークは,以下のスライドに掲載されている画像の奥に見える城と,さらに奥にある巨大な樹木だが,どちらも巨大すぎてビューポイントの画面に収められなかった。
![画像ギャラリー No.028のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/028.webp) |
![画像ギャラリー No.029のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/029.webp) |
重要な要素を画面に収められないため,良いレイアウトを作ることが難しい状態に陥ったが,フロム・ソフトウェアの3Dグラフィックセクションはプレイヤーが画面の外までカメラを動かす前提でレイアウトすることにした。すなわち,ランドマークが中途半端に映っていれば,プレイヤーは能動的にカメラを動かして全体像を見ようとするだろうと考えたのである。
![画像ギャラリー No.030のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/030.webp) |
以下のスライドに掲載された画像は,完成したレイアウトを通常よりも画角を広げて撮影したものだ。プレイ中にこの画面を見ることはできないが,カメラを動かすことでこのような全体像を想像してもらおうと考えた。言い換えると,「巨大な絵画を近い距離から鑑賞するような体験」を狙ったそうだ。
![画像ギャラリー No.031のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/031.webp) |
![画像ギャラリー No.032のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/032.webp) |
「ELDEN RING NIGHTREIGN」の事例紹介
「NIGHTREIGN」からは,ゲームの1サイクルの終点にあたるボスエリアの事例が紹介された。本作のボスエリアは,「どのボスでも地形が共通で,非常に広い」「地形に段差がなく,移動や攻撃などのあらゆる動きを阻害しない」という2つの空間的な特徴を持つ。
とくに本作ではボスがさまざまな動きを見せるため,ボスエリアは担当のプランナーやアニメーター,リガーと細かく擦り合わせをしながら制作が進められた。空間的な特徴からボスエリアのデータを作っていくにあたり,地形には「基本的に緩やかなスロープ形状であること」「ゲーム内の動作や各操作に無理のない高低差であること」,そして配置物には「接触などにより敵の行動を妨げないこと(コリジョンを基本的に無視できること)」が求められたという。
それらの要件を満たす理想のマップが,以下のスライドに掲載された画像だ。何もない平坦なマップで,行動や認識を絶対に阻害しないものとなっている。
![画像ギャラリー No.033のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/033.webp) |
また「NIGHTREIGN」のボスとボスエリアは,後半戦に入るとカットシーンを挟むことなく,シームレスに見た目が変化する。そのためボスエリアの制作にあたっては,後半戦に入るときに「コリジョン構成の変わる変動が行えない」ことも要件となる。
例えば巨大な岩のような,コリジョンを含む配置物が後半戦に入るときに出てきてしまうと,プレイヤーキャラクターやボスがコリジョンの中に入り込んでしまって動けなくなる可能性が生まれてしまうのだ。
![画像ギャラリー No.034のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/034.webp) |
![画像ギャラリー No.038のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/038.webp) |
以上から,「NIGHTREIGN」のボスエリアは基本的に「空と地面を主体でなければならない」という強い制限のもと,印象の強い画を作る必要が生じたのである。その具体例として「三つ首の獣」「喰らいつく顎」「闇駆ける狩人」の3つが紹介された。
三つ首の獣の後半戦におけるボスエリアは,朝焼けの地平線と印象的な空,そして高さのある幻影の空で構成されている。この構成は,すべてのボスの後半戦の基準となるものとして,最初に考えたものとのこと。
また地形や配置物などのボスエリアに共通する要件以外の制限はなかったことも,基準とするに相応しかったそうだ。
![画像ギャラリー No.036のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/036.webp) |
このボスエリアを作るにあたって最初に取り組んだのは,制限である空と地形による基本構成だ。ボス後半戦の体験を盛り上げるべく,品質を高めるよりも印象を強めることが優先された。朝焼けという馴染みのある強いライティングと,現実では見ることのないような空の情報を違和感になる要素として,全体の印象を強めている。
![画像ギャラリー No.037のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/037.webp) |
次に全体の単調さを改善するべく,動きのある幻影の旗を地平線に向かって柱のように配置した。これにより画面左右の情報の違いが生じ,単調さをなくしつつ,奥の空間への視線誘導の効果をもたらしている。この旗は,各種要件・制限を事前にコンセプトアーティストと共有し,コリジョンがなくとも違和感のない配置物としてデザインしてもらったそうだ。
![画像ギャラリー No.038のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/038.webp) |
さらにフォグを加えることで,広く平坦な地形と奥にある地平線の単調さが改善された。また画面の中央から上半分にグラデーションをかけ,明度と色相の変化を付けている。
![画像ギャラリー No.039のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/039.webp) |
より品質を高めるため,最遠景に地形を追加し空間の広がりを演出し,さらに単体で配置している炎のエフェクトのほかに,地形を這うような炎の表現を追加して,画面の印象を強めている。とくに後者は,全体的な視線誘導の流れに逆らっているため,違和感になる要素としても機能し,印象をより強める効果につながっている。
![画像ギャラリー No.040のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/040.webp) |
![画像ギャラリー No.041のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/041.webp) |
![画像ギャラリー No.042のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/042.webp) |
喰らいつく顎のボスエリアは,空に空いた巨大な穴が瞳を想起させ,また穴の周囲には激しく喰いちぎったような表現を加えた,中央に強く視線を誘導する構成となっている。地面にある柱状の配置物も,全体の流れに逆らわないよう配置された。
![画像ギャラリー No.043のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/043.webp) |
このボスエリアを作るにあたっても,最初に行ったのは基本的な構成を詰めることだ。
まず印象的な空と共通の地形に,縦の色変化を持たせるフォグを設定。そこに厚みのある別のフォグを,黒い雲が地形を覆うように配置し,地平線のシルエットを谷型に変化させている。これには,地平線の単調なシルエットを隠しつつ,このシーン固有の異質さを表現する効果もあるとのこと。
![画像ギャラリー No.044のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/044.webp) |
![画像ギャラリー No.045のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/045.webp) |
ここまでの作業で,基本的な中央への視線誘導と自然な奥行きは実現できているのだが,空のインパクトがやや薄い。そこで中央部をさらに際立たせるために,マテリアル上で減算処理を行うメッシュをフィルターのように重ねている。これには空のインパクトを引き出しつつ,穴とそれ以外の空間における違和感を出して,マップ全体の印象をさらに強める狙いがあるという。
![画像ギャラリー No.046のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/046.webp) |
このボスエリアを作っていく過程では,「発光表現が眩しくて,戦闘に支障が出る」「配置物に敵が隠れてしまって,動きが見えない」という,新たに2つの要件が生じたという。そのため,「配置物の表現をかなり抑えめに作る」必要が生じた。
![画像ギャラリー No.047のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/047.webp) |
![画像ギャラリー No.048のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/048.webp) |
そこで配置物の発光表現を全体的にかなり抑え,かつ透過させることで裏側をしっかり見せることになった。また,それだけでは配置物の幻影としての存在感がなくなるため,地面との接地面に揺らぎの表現を追加している。
![画像ギャラリー No.049のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/049.webp) |
![画像ギャラリー No.050のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/050.webp) |
![画像ギャラリー No.051のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/051.webp) |
闇駆ける狩人のボスエリアは,暗闇の中で黄金の夜明けを迎えたイメージで,これまでの事例とはまた毛色の異なる,縦の情報を強化したレイアウトになっている。
![画像ギャラリー No.052のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/052.webp) |
このボスエリアは,最初に空とフォグで基本となる見た目を作ったとのこと。基本的な考え方はこれまでの事例と同じく,空で印象を強めて,フォグで縦と奥行きのグラデーションを作っている。
![画像ギャラリー No.053のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/053.webp) |
次にメインの特徴となるライトシャフトを,画面左右の単調さをなくすことや,ある程度グループ単位にすることを意識しつつ配置していく。とは言え,ライトシャフトだけでは縦の情報による単調さが出てしまうため,雲の明度や色相に変化を付けて,斜めの情報が追加された。
![画像ギャラリー No.054のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/054.webp) |
![画像ギャラリー No.055のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/055.webp) |
地形には,戦闘の妨げにならない大きさと輝度で作った配置物を置いて,単調さを軽減する。ちなみに,この配置物はコンセプトアートから採用したものだそうだ。
![画像ギャラリー No.056のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/056.webp) |
このボスエリアの追加要件は,「地面から発生するボスの攻撃が多い」ことだ。そのため地面に目立つものを多数配置してしまうと,それら攻撃の予兆の視認が難しくなってしまう。
![画像ギャラリー No.057のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/057.webp) |
そこでこのボスエリアでは,プレイヤーキャラクターのすぐ近くに配置物がある頻度を抑えるべく,配置間隔を広めにしている。加えて,ピンポイントに配置バランスを調整できるような工夫もしたそうだ。
![画像ギャラリー No.058のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/058.webp) |
さらに,それぞれのシェーダーにカメラ前での配置物のフェード処理を入れ,プレイヤーキャラクターの足元に発生する攻撃予兆をしっかり視認できるようにしている。
![画像ギャラリー No.059のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/059.webp) |
![画像ギャラリー No.060のサムネイル画像 / フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/060.webp) |
CEDEC 公式サイト
4Gamer「CEDEC 2025」記事一覧
- 関連タイトル:
 ELDEN RING NIGHTREIGN
ELDEN RING NIGHTREIGN
- 関連タイトル:
 ELDEN RING NIGHTREIGN
ELDEN RING NIGHTREIGN
- 関連タイトル:
 ELDEN RING NIGHTREIGN
ELDEN RING NIGHTREIGN
- 関連タイトル:
 ELDEN RING NIGHTREIGN
ELDEN RING NIGHTREIGN
- 関連タイトル:
 ELDEN RING NIGHTREIGN
ELDEN RING NIGHTREIGN
- この記事のURL:
キーワード
- PC:ELDEN RING NIGHTREIGN
- PC
- RPG
- MO
- バンダイナムコエンターテインメント
- ファンタジー
- フロム・ソフトウェア
- プレイ人数:1〜3人
- プレイ人数:1人
- 協力プレイ
- PS5:ELDEN RING NIGHTREIGN
- PS5
- PS4:ELDEN RING NIGHTREIGN
- PS4
- Xbox Series X|S:ELDEN RING NIGHTREIGN
- Xbox Series X|S
- Xbox One:ELDEN RING NIGHTREIGN
- Xbox One
- イベント
- ライター:大陸新秩序
- CEDEC/コ・フェスタゲーム開発者セミナー
- CEDEC 2025
(C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C)2024 FromSoftware, Inc.
(C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C)2024 FromSoftware, Inc.
(C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C)2024 FromSoftware, Inc.
(C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C)2024 FromSoftware, Inc.
(C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C)2024 FromSoftware, Inc.



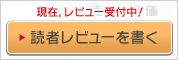
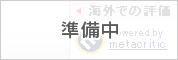



![フロム・ソフトウェアが語る「ELDEN RING」の背景レイアウト術。実例から世界の作り方を紐解く[CEDEC 2025]](/games/866/G086614/20250724066/TN/061.webp)