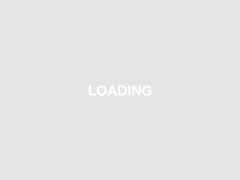イベント
プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/001.webp) |
ここ数年で急速に浸透した感のあるマーダーミステリーだが,プレイしたことのない人に,その面白さを伝えるのは非常に難しい。なにぜ謎解きをベースにしたゲームなだけに,同じシナリオは2度プレイできず,詳細に説明してしまうと必然的にネタバレになってしまうからだ。
この講演は,そんなマーダーミステリーの構造について,デジタルの推理ゲームとの違いに着目しながら解説したものとなっていた。登壇したのは,デジタルゲームとマーダーミステリーの双方を手がけた経験があるという,日本マーダーミステリー作家協会の檜木田正史氏だ。
あくまでマーダーミステリーを知らない人向けの解説なので,すでに“沼”にどっぷり浸かっている人には言わずもがなの内容かもしれない,そこはどうかご了承のうえ,お付き合いいただけたら幸いだ。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/002.webp) |
日本マーダーミステリー作家協会 公式サイト
檜木田氏を魅了した対面型推理ゲーム
登壇者の檜木田氏の本業はゲームのシナリオライターだ。古くは初代PlayStationの時代に「金田一少年の事件簿」シリーズに関わったほか,「3年B組金八先生 伝説の教壇に立て!」「428〜封鎖された渋谷で〜」「流行り神2 警視庁怪異事件ファイル」など,名だたるアドベンチャーゲームのシナリオに参加した経歴を持っている。
マーダーミステリーにハマったのは2019年頃で,プレイはもちろん,それまでの経験を生かしてオリジナルの作品を生み出し,販売も手がけている。近年は「日本マーダーミステリー作家協会」を発足し,所属する作家と共にどうすればマーダーミステリーが面白くなるかを日々探求しているとのこと。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/003.webp) |
今さらではあるが,マーダーミステリーとは数人のプレイヤーが一堂に会し,テーマとなる殺人事件などの犯人を特定していく会話型の推理ゲームだ。
参加者には,自らが扮する人物の経歴などが書かれた設定書(ハンドアウト)が配られ,その中で自身の役割や,事件当日何をしていたかを知ることになる。プレイヤーの中にはもちろん犯人役を割り振られる人もいて,その場合,設定書にはどうやって殺人を行ったかといった情報が記載されるのである。
犯人役のプレイヤーはそれを隠しつつ立ち回り,それ以外のプレイヤーは犯人を特定すべく推理と追求を行っていく。そうして最後に誰が犯人なのかを投票で決め,間違っていれば犯人の勝ち,正解であればそれ以外の人の勝ちとなる。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/004.webp) |
このような基本フォーマットの元,さまざまな趣向を凝らしたタイトルがパッケージとして販売されており,またインターネット上でもプリントアウトして遊べる形態のものや,PCやスマートフォンを使ってオンラインで遊ぶことを前提にしたものが,個人制作によるタイトルも含め,数多く流通している。
さらにマーダーミステリーをプレイするための店舗――マーダーミステリーカフェのような専門店も人気を集めており,プロのゲームマスターに進行を担当してもらい,リッチなプレイ体験が楽しめる場として愛好家に親しまれている。このように,現在のマーダーミステリーは,多種多様なスタイルで広がり続けているのだ。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/005.webp) |
デジタル推理ゲームとマダミスの本質的な違い
デジタルの推理ゲームとマーダーミステリーの両方を手がけたことのある檜木田氏は,その違いについて解説を行った。
デジタルの推理ゲームは主にアドベンチャーゲームの文脈で発展を遂げてきたジャンルであり,あらかじめ用意された選択肢によってストーリーや結末が分岐する仕組みなので,どんなに複雑なものであっても,物語がレールから外れることはない。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/006.webp) |
一方,マーダーミステリーはスタート(事件)とゴール(犯人当て)が決まっているのみで,その間の議論はプレイヤーの自由な行動に委ねられている。あらかじめレールが敷かれていない,“自由な行動”を容認する点がデジタルゲームとの差異ではあるが,それによりプレイヤーが迷走してしまったり,サボってゲームに参加しなくなる人がいたり,あるいはプレイヤー同士がケンカをし始めたりといった,自由ゆえの問題が生じる可能性があり,これを防ぐゲームデザインが求められる。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/007.webp) |
そのために必要なのが,ゲームにおけるルールやマナーだ。
ここでいうルールは,制限時間や議論の方法,投票の手段,カード取得の手順といった,プレイヤーの動きを制御するものを指している。一方のマナーは,「他人のハンドアウトを覗き見ない」「キャラクターになりきってロールプレイする」「感情的になりすぎない」といった,プレイヤーが共有すべき了解事項であり,これによってゲームプレイを円滑に進められるとした。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/008.webp) |
またプレイヤーの目的を明確にし,行動に指針を与える「ミッション」も重要だという。
犯人以外のプレイヤーなら,「犯人に最多票を入れる」が当然メインのミッションになるが,それに加えてサブとなるミッションが設定されることがある。達成すれば,より高得点が狙えるメリットがあり,さらにプレイヤーがこれを目標として行動することで,迷走を防ぐ効果もあるという。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/009.webp) |
ミッションとは別に,「被害者を殴った」「金庫の宝石を盗んだ」といった「秘密」が設定されることもある。プレイヤーはそれがバレないようにゲームを進める必要があり,これにより余計なことをしなくなるそうだ。
デジタルゲームでは,ゲームの進行に伴い物語もおのずと進んでいくものだが,マーダーミステリーでは議論が停滞し,物語が進まなくなることがある。これを防ぐための工夫も用意されている。
例えば,マーダミステリーではカードを使って事件の手がかりを入手するが,時間経過で引けるカード(山札)を変化させることで,「新たな死体の発見」「外部からの新たな情報」といった,新たな展開をゲームに盛り込める。ほかにもゲーム後半に強制的なイベントを仕込んだり,プレイヤーに追加のハンドアウトを渡すといった手法でも,物語に劇的な変化を生み出せるとのこと。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/010.webp) |
檜木田氏は,マーダーミステリーのデザインを「作者vs.プレイヤーではない」と説き,推理ゲームや推理小説との違いを説明した。後者では,制作者側が用意した謎に読者側が挑戦する,いわゆる「読者への挑戦」が成立しうるが,マーダーミステリーは「プレイヤーvs.プレイヤー」のゲームであり,「作者vs.プレイヤー」の構図になりえない。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/011.webp) |
檜木田氏は,これをアリーナの中で戦うPvPに例え,武器や能力が異なるプレイヤーが,さまざまな地形を利用して戦う構造こそが,面白いマーダーミステリーを生み出す秘訣だと語った。
マーダーミステリーの作家が手がけるのは,このアリーナの作成&整備であり,どんなアリーナを作れば物語が面白くなるのか,そしてプレイヤーにどんな武器や能力を持たせればバトルが盛り上がるのか,そうした思考でゲームを作り上げていくのだ。
ここで大事なのは,プレイヤーごとの難度や満足度が均一になるようバランス調整することだ。違う立場のキャラクターでプレイしたとしても,難度は全員ほぼ同じで,トリックも簡単過ぎず難しすぎないレベルを心がける。なお檜木田氏のタイトルでは,犯人が当てられる確率は30%程度に設定するそうだ。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/012.webp) |
マーダーミステリーは対人戦であるため「極めて人間的」なこともデジタルゲームとの違いとして挙げられた。
カードやシナリオの情報を共有する,情報を忘れる,誤解するなど,プレイヤー次第で展開は大きく変化する。カードピックによるランダム性もあって,誰がどのカードを引くかは予測できないし,プレイヤーがどう配役されるかでも進行は読めなくなる。ゆえに前回のゲームと同じ振る舞いをしたとしても,どうしたって疑心暗鬼は発生する。それこそがマーダーミステリーの楽しいところだと氏は語っていた。
そしてゲーム終了後に行う「感想戦」もまた,マーダーミステリーの醍醐味だ。全員で今回のプレイを語り合い,個人の視点では見えなかったシナリオ全体の流れや,個々のプレイヤーの動きを把握する。ここで誰かのファインプレイを初めて知ることもあって,非常に楽しい時間なのだそうだ。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/013.webp) |
マダミスを盛り上げるためのさまざまな手法
講演の後半では「マーダーミステリーの盛り上げ方」として,クリエイターがゲームを盛り上げるために,どんな工夫をしているのかの紹介が行われた。
ミッションのジレンマ
一つ目は,前半でも話題に登った個人ミッションを,あえて対立が発生するように仕向けて物語を盛り上げるテクニックだ。
例えば,「ある人物は特定のアイテムを奪わなくてはならず,別の人物はそれを守らなければならない」という具合に,プレイヤーが衝突せざるを得ないミッションを用意しておくのである。ほかにも「犯人を見つけだす重要なヒントである一方で,それを明らかにすると自身の浮気がバレてしまう」といったように,登場人物の内面に葛藤を埋め込む方法もある。このように「どのミッションを優先するか」というジレンマが,物語に大きなドラマを作り出すわけだ。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/014.webp) |
エンディング分岐
マーダーミステリーには複数の結末が用意されることが多く,これはプレイヤーの行動やミッションの達成状況によって辿り着く先が変化するのがほとんどだ。とくに犯人が特定されたか否かは重要で,これによりプレイヤーは自身の選択が物語に影響を与えたことを実感できる。物語への没入感を強化する手法の一つといえる。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/015.webp) |
アクションフェイズ
マーダーミステリーの中には,最後の議論が終わり犯人当ての投票に移る直前に「アクションフェイズ」を用意しているものが少なくない。実行できるアクションはハンドアウトに記載されている場合や,プレイヤーが自由に発想できる(そしてゲームマスターがその可否を判断する)場合があるが,その行動でエンディングが変化することもある。
例えば犯人が最後に誰かを道連れにしようとしたり,それを阻止しようとしたりするアクションが典型例で,実際にそれを実行するか否かの葛藤も含めて,物語を盛り上げる大きな要素になっている。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/016.webp) |
変わり種
マーダーミステリーは今なお進化を続けているジャンルであり,王道や定番から外れたバリエーションもまた多く存在する。
その一例として挙げられたのが,2人プレイ専用のマーダーミステリーだ。2人しかプレイヤーがいなければ,あっという間に犯人が分かりそうなものだが,そこに仕掛けや捻りが加えられおり,一筋縄ではいかないところに面白みがある。
また「ペアマダミス」というものもあって,これはペアを組んだ2人でほかのペアと対決するタイプのマーダーミステリーだとか。さらには「謎解きゲーム」や「LARP(Live Action Role-Playing)」といった,ほかのジャンルと融合したハイブリッドなもの,謎解きよりも物語体験に比重を置いたものなど,さまざまなタイプの作品が存在している。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/017.webp) |
単なる推理ゲームの枠を超え,プレイヤーの感情を揺さぶる物語体験として進化を続けるマーダーミステリージャンル。檜木田氏の日本マーダーミステリー作家協会でも,より面白い作品を作り出すための取り組みを進めているとのこと。
本稿でマーダーミステリーに興味を持った人,また興味はあったが機会がなかった人は,この機会に最寄りの専門店などをチェックし,実際にプレイしてみてはいかがだろうか。
CEDEC 公式サイト
4Gamer「CEDEC 2025」記事一覧
- 関連タイトル:
 マーダーミステリー 金田一少年の事件簿
マーダーミステリー 金田一少年の事件簿
- この記事のURL:


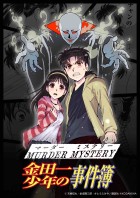
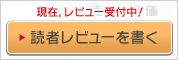
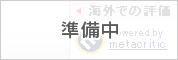






![プロが指南する「マーダーミステリー」の作り方。デジタルゲームの元クリエイターが,その構造の面白さやゲームデザインのコツを語る[CEDEC 2025]](/games/668/G066849/20250731001/TN/018.webp)