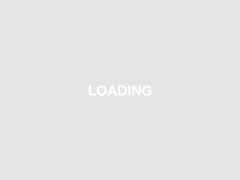イベント
「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]
CEDEC 2025のセッション「『Rise of the Ronin』幕末オープンワールドでTeam NINJAアクションを実現せよ!」では,制作の過程で見えた課題と,それに対するアプローチが紹介された。
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/001.jpg) |
「Rise of the Ronin」公式サイト
小規模なフローを作ってから検証していく
セッションに登壇したのは,ディレクターの渋谷隼人氏(レベルデザイン担当),藤崎健雄氏(アクション担当),嵯峨隆之氏(UI・RPG担当)だ。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/002.jpg) |
まずは渋谷氏がレベルデザインについて語った。本作のレベルデザインでは,「リアリティライン」をリアルに寄せたという。倒幕派,佐幕派,海外勢力が入り乱れる戦いと因縁が核となる以上,あまりにもファンタジックな内容にはしにくい。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/003.jpg) |
しかし,ゲームとしての面白さを追求するためなら,ある程度の誇張は許容した。例えば,ゲームスタート時の横浜は本来よりも少し未来の姿で表現されている。また,江戸城の天守閣は明暦の大火により焼失し,この時代にはないのだが,ストーリー上の象徴として登場する。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/004.jpg) |
本作の特徴的なシステムである「因縁システム」は,キャラクターとの出会いによって発生し,共闘や交流で深まる。これは成長要素であると同時に,プレイヤーが作中の世界に影響を与えている感覚を味わうための役割も持つ。渋谷氏は「今日,私と聴講者とのあいだにも因縁が成立した」と語り,会場を和ませた。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/005.jpg) |
本作の物語は,黒船来航から江戸城無血開城までを描いている。第一章の横浜では倒幕派との因縁,第二章の江戸では佐幕派との因縁を結び,そして第三章の京都を経て,プレイヤーが選んだ勢力と共に歴史の転換点へと向かう構成だ。
Team NINJAにとって初のオープンワールド作りは,横浜から始まった。従来の制作フローではレベルデザイナーがステージドラフトを作成していたが,今回は広大な範囲を扱うため,背景チームが古地図を元に大まかな地形,海岸の侵食情報など反映したワールドドラフトを制作した。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/006.jpg) |
そこからディレクターやレベルデザイナーが加わり,距離感や規模感の調整を繰り返す。その後,従来のフローに近い形で,レベルデザイナーがコンテンツ部分をステージドラフト上で作っていった。
この段階で,オープンワールド部分とミッション部分のバランスや変遷を確認し,ゲームプレイを通してのワールドの広さを検証するため,まずは重要なシステムを含む小規模な流れを制作する。
1. 横浜にたどり着いた主人公が賊に襲われた村を訪ねる
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/007.jpg) |
2. 龍馬と徒党を組んで共に賊を倒し因縁を結ぶ
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/008.jpg) |
3. 滑空装置で横浜の街へ
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/009.jpg) |
4. 龍馬と再会,倒幕派とも因縁を結ぶ
5. 徒党を組み,牢屋敷で吉田松陰を助ける
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/010.jpg) |
こうしたフロー検証で作られた範囲は,横浜の街と山1つ分ほどの規模だった。要領を掴んだあとは,そのほかのエリアも順調に拡大……したわけではなかった。しかし「それこそがゲーム制作の楽しいところ」と,渋谷氏は考えている。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/011.jpg) |
大きな課題は2つあった。まず,主要なイベントが都市部に偏りすぎてしまった。史実をベースにしたがゆえの問題だが,広いワールドを探索する理由がなくなり,開放感も得られない。
改善策としては,遠方の城跡などに向かうミッションを作り,そこまでの移動手段を自由にしたり,道中に遊びの要素を配置したりした。ミッションの内容も,滑空を使うかどうかで展開が変わるようにしている。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/012.jpg) |
結局のところ,史実を元にしたゲームであろうとも,プレイヤー体験が最重要であることを再確認したという。オープンワールドは従来型の開発より,ゲームの設計以後に課題を発見することが多く,これまで以上に創造力を求められるものだった。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/013.jpg) |
もう1つの課題は,舞台が横浜に移った際のリニア(一本道)感だ。主人公の背景が固まり,プロローグ編が増えたこと,横浜に移動後は龍馬と出会うイベントを必ず通過すること,そしてチュートリアルが「渋滞」してしまったことで,まったくオープンな感じがしなかった。
そこで,横浜編のスタート地点を変え,周辺に探索できるエリアも新たに用意した。プレイヤーがある程度自由に探索したり,遊びの要素を楽しんだりしつつ,その出口で龍馬と出会える構成にしたわけだ。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/014.jpg) |
このようにプレイヤー体験が大きく変わるポイントは死角になりやすいため,開発の進行に合わせて定期的に検証すべきという知見を得たそうだ。
RPG要素の調整とUIの工夫で体験を磨きあげる
続いて,嵯峨氏がRPG的な調整とUIについて語った。
本作はレベル上昇やスキル習得により,キャラクターが強化される。しかし,オープンワールドであるがゆえにプレイヤーの行動は予測不能だ。メインイベントの合間にプレイヤーがどの程度寄り道し,技などを習得するかを事前に把握することは難しい。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/015.jpg) |
結局のところ,スマートな解決策はなく,テストプレイヤーの進行ルートやパラメータ変動をログとして抽出し,それを参考に導線を設計したり,バランス調整を行うことにしたという。
また,プレイヤーは「地図を埋めようとする」意欲が強い。仮に遊びの要素をコンプリートされても(それによってキャラクターが強化されても),ゲームが極端に簡単にならないように意識した。
本作では経験値をミッション報酬に偏らせ,レベル上昇をコントロールしたが,その結果,低レベルクリアなどの自由な遊びが制限された側面もあった。嵯峨氏は「そのゲームのテーマや内容に合わせ,プレイヤーが何を求めているかを見極めて調整すべき」と語った。
次はマップのUIやUX(ユーザー体験)だ。
これまで開発してきたゲームでは補助的な役割だったマップが,本作ではとても重要だった。ゲームに集中してもらうためには,マップ画面が快適であると同時に,何を見せるか,見せないかの判断が大切となる。
そこで,探索によって「土地との因縁」を深めると,施設や収集物のアイコンが徐々にオープンになっていく仕組みを導入した。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/016.jpg) |
初期は何も見えないが,探索によってファストトラベル地点や敵の出現ポイントが分かるようになる。因縁を深めるにつれて寄り道要素や収集要素の位置が表示され,マップの霧も晴れていく。情報の開示タイミングにより,プレイヤーに新たな目的地を見つけてもらい,興味を持続させたわけだ。
これは開発内部で意見が分かれたことでもあったが,舞台が広大なゲームでは,マップに表示されていない目的地はプレイヤーにとって「無い」も同然であり,こうした仕組みになったという。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/017.jpg) |
バトルを盛り上げた4つのアプローチ
新撰組をこよなく愛するという藤崎氏は,バトルについて4つのアプローチを解説した。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/018.jpg) |
1つ目は「幕末世界を快適に踏破できる移動アクション」だ。本作の舞台はTeam NINJA作品では前例のない,広大でさまざまな場所に行けるワールドだったため,徒歩以外にも滑空,馬,鍵縄,泳ぎなどを用意。これらの移動手段をただ存在させるだけでなく,相互にスムーズにつながる操作性を目指した。
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/019.jpg) |
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/020.jpg) |
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/021.jpg) |
2つ目は「オープンワールドでのバトルデザイン」。手触りが良く,歯応えあるバトルの実現には,激しい攻撃を行う強敵と,それを撃破する達成感が必要になる。ただ,作品のリアリティライン的に異形や妖怪を出さないことが早い段階で決まり,敵のほとんどは人間となる。
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/022.jpg) |
そこで導入したのが,「石火(せっか)」というアクションである。敵の攻撃をさばくパリィ的なアクションであり,時代劇のようなチャンバラ感を演出する,本作のバトルの核となるものだ。
![画像ギャラリー No.023のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/023.jpg) |
しかし,オープンワールドではどんな順番で敵と遭遇するかをコントロールできない。しかも人間に大げさな動きをさせると不自然になるため,初見では敵に対処しにくい問題も生じた。
そこで,敵の戦い方を「武器」と「流派」の両軸にまとめた。
敵が持っている武器や大まかな雰囲気から,有利な相性が判断できるようになっており,その相性で石火を決めると大きくのけぞらせて,攻撃のチャンスを生み出せる。
![画像ギャラリー No.024のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/024.jpg) |
また,敵の流派ごとの構えから攻撃を予想できたり,プレイヤーが流派を使ってみることで,相手にしたときに戦いやすくなったりする効果も狙っている。歯応えあるバトルを楽しんでもらうため,さまざまな形で情報を伝えていたというわけだ。
そして流派を設けたことで,薩摩藩士は猿叫させたり,薩摩示現流の「蜻蛉の構え」で威圧したりと,相手のバックグラウンドも描けるようになった。ただし,理知的な大久保利通だけは猿叫を封印している。
![画像ギャラリー No.025のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/025.jpg) |
近藤 勇とは数回戦うことになるが,刀から大太刀,そして大剣へと武器を変化させている。構えは天然理心流の平正眼のままだが,武器だけが大型化していくことで,近藤の実直で不器用なキャラクター性を表現したという。
![画像ギャラリー No.026のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/026.jpg) |
3つ目は「史実を元にしたボスのバトルスタイル設定」。本作のボスは史実の人物であり,どうバリエーションを持たせるかが課題だった。
まずは各勢力に傾向を持たせた。佐幕勢力は伝統的な武器と戦い方を突き詰めた強さで,井伊直弼や勝 海舟,新選組などが該当する。
![画像ギャラリー No.027のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/027.jpg) |
一方,倒幕側は派手なバトルスタイルで,海外由来の武器や近代武器を取り入れている。西郷隆盛も倒幕の姿勢を鮮明にしてからは,アームストロング砲などを使うようになる。
![画像ギャラリー No.028のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/028.jpg) |
そして海外勢力のキャラクターたちは,いかに欧米列強が技術で先行していたかを際立たせるため,オーバーテクノロジー気味に描かれた。火砲を備えた銃剣を扱うジュール・ブリュネ,ジェットブーツ装備のアーネスト・サトウなど,史実ネタも積極的に取り入れ,拡大解釈した演出になっている。
![画像ギャラリー No.029のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/029.jpg) |
4つ目は「バトルで伝えるストーリー進行」だ。本作には主人公の「片割れ」が登場し,序盤で行方不明になるが,再会すると敵対関係となる。
片割れはもう1人の主人公であり,歴史の裏で暗躍し,要所でプレイヤーの前に立ちふさがる。そこをストーリーの節目として演出する必要があった。
![画像ギャラリー No.030のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/030.jpg) |
片割れもまた「因縁」によって成長するボスと設定し,これまで接した相手の技を取り込んでいくことになった。義手に仕込まれたギミックも,ワイヤーや火砲,放電機構,そしてパイルバンカーと段階的に増えていく。これは海外勢力とのつながりを示すものでもある。
![画像ギャラリー No.031のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/031.jpg) |
最後に,渋谷氏は「『Rise of the Ronin』という作品,オープンワールドアクションRPGの制作,そして幕末という時代に興味を持っていただけたら,Team NINJA一同は本当に幸せです」と聴講者に呼びかけ,セッションを締めくくった。
![画像ギャラリー No.032のサムネイル画像 / 「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/032.jpg) |
「Rise of the Ronin」公式サイト
「CEDEC 2025」公式サイト
4Gamer「CEDEC 2025」関連記事一覧
- 関連タイトル:
 Rise of the Ronin
Rise of the Ronin
- 関連タイトル:
 Rise of the Ronin
Rise of the Ronin
- この記事のURL:
キーワード
- PS5:Rise of the Ronin
- PS5
- アクション
- RPG
- CERO D:17歳以上対象
- CERO Z:18歳以上のみ対象
- Sony Interactive Entertainment
- Team NINJA
- コーエーテクモゲームス
- プレイ人数:1人
- 歴史物
- PC:Rise of the Ronin
- PC
- イベント
- ライター:高橋祐介
- CEDEC 2025
(C)2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
(C)2024-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
- 【PS5】Rise of the Ronin Z version ( ライズオブローニン )【早期購入特典】 4 つの流派・武器・防具の早期アクセス(封入) 【Amazon.co.jp限定】オリジナル湯呑 付【CEROレーティング「Z」】

- ビデオゲーム
- 発売日:2024/03/22
- 価格:4904円(Yahoo)



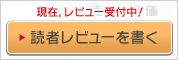
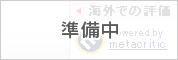




![「Rise of the Ronin」の"幕末の世を腕を頼みに渡り歩く"感覚はどう生み出されたのか[CEDEC 2025]](/games/657/G065716/20250729055/TN/033.jpg)